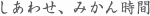こんにちは。野菜ソムリエの玉之内祐子です。
真冬においしい野菜として菜の花やブロッコリーなど
蕾を食べる野菜が数多くありますが、
今回はその中でも少し珍しい「紅菜苔(コウサイタイ)」をご紹介します。
紅菜苔はチンゲンサイやターサイ、ハクサイなどと同じくアブラナ科の野菜で、
和名をベニナバナと言います。
その名の通り、茎や葉柄が赤紫色で特徴的な見た目をしています。
菜の花と同じく、蕾の付いた花芽と茎や葉を食べる野菜で、
菜の花よりも寒さに強く、
寒ければ寒いほど茎の赤紫色が濃く鮮やかになるとされています。
ただ、この赤紫色の色素はポリフェノールの一種で水溶性のため、
茹でると葉と同じ緑色に変化します。
やわらかく、独特な甘みとぬめりがあり、
苦みがほとんどないので食味の良さは菜の花を超えるかもしれません。
炒め物やおひたし、からし和えなどにするのがおすすめです。
レア野菜ではありますが、見かけたらぜひ手に取ってみてくださいね。
|
あけましておめでとうございます。
野菜ソムリエの玉之内祐子です。
1月7日と言えば、七草粥。
一年の無病息災を願い、春の七草を入れたお粥を食べる習慣です。
春の七草とは、せり・なずな・ごぎょう・はこべら
ほとけのざ・すずな・すずしろの七種の野菜を指します。
しかし、年末年始のごちそうで疲れた胃腸を労わり、
冬場に不足しがちなビタミンやミネラルを補うという観点から、
七草粥は必ずしもこの7種である必要はありません。
冷蔵庫にある野菜で代用してもOK。
例えばビタミン類だけでなく、
カルシウムや鉄なども豊富な小松菜、クレソン、
チンゲンサイ、ホウレンソウあたりは簡単に代用できそうです。
他にもβカロテンたっぷりで彩りにもなるニンジンや、
香り・風味をプラスするのにセロリやシソ、コリアンダーもおすすめです。
味付けも使う野菜によって洋風にしたり、中華風にしたり。
今年の七草粥はオリジナルアレンジを楽しんでみてはいかがでしょうか。
|
こんにちは。野菜ソムリエの玉之内祐子です。
年の瀬ですね。今回はおせち料理の定番「田作り」の
塩みかんアレンジをご紹介します。
「塩みかん田作り」
【材料】(作りやすい分量)
カタクチイワシ(素干し) 50g
ごま 大さじ1
〇塩みかんマリネの素 小さじ1
〇酒 大さじ1
〇砂糖 大さじ2
〇しょうゆ 大さじ1弱
〇水 小さじ1
【作り方】
1.フライパンにカタクチイワシを入れて弱火でゆっくり(8~10分程度)乾煎りする。
2.1のイワシが手でパキッと割れるくらい火が通ったら一旦バットに取り出す。
3.フライパンに〇の調味料を入れて泡が立つまで煮立て、とろみが付いてきたら2のイワシを戻してタレにからめる。
4.全体が絡んだら火を止め、固まらないようにサラダ油(分量外)を回しかけて軽く混ぜ、重ならないようにバットに広げる。
5.ごまをふって冷ます。
しょうゆと砂糖のあまじょっぱい味付けに塩みかんマリネの素がよく合います。
一味違う風味の田作り、ぜひお試しください。
|
こんにちは。野菜ソムリエの玉之内祐子です。
クリスマスはもちろんですが、
年末年始はお肉やケーキなどおいしいものを食べる機会がぐっと増えますよね。
おいしいものには脂質や糖質がたっぷり入っていることが多いため、
ぜひ一緒に野菜・果物もとりたいところです。
野菜や果物にはビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれていて、
そのビタミンやミネラルは脂質や糖質の代謝を促してくれるものも多いのです。
また、色鮮やかな色素を持った野菜や果物は見た目にもクリスマスにぴったり。
おすすめなのは「ブロッコリー」やカリフラワーの仲間の「ロマネスコ」、
甘みたっぷりの「フルーツトマト」や茹でると真っ白で美しい「レンコン」。
果物ですが、サラダにもおすすめの「アボカド」、
また「イチゴ」や「紅まどんな」も旬をむかえています。
お酒に生のフルーツを搾り入れるのもおすすめです。
ぜひホリデーメニューに取り入れて彩りを添えてみてはいかがでしょうか。
|
こんにちは!野菜ソムリエの知久です。
もうすぐクリスマスということで、
最近流行っている焼きカリフラワーと塩みかんを使ったひと品をご紹介したいと思います。
【材料】(2人分)
・カリフラワー‥1/2個
・豆腐‥130g
・ほうれん草‥50g
・いりごま‥大さじ2
・塩みかん(完熟)‥小さじ1弱
・ごま油‥大さじ1
【作り方】
①豆腐はキッチンぺ―パーに包み、お皿を乗せて1時間ほど水切りをする。
ほうれん草は下茹でをしてしっかり水気を切る。
②いりごま・塩みかん・①をフードプロセッサーに入れペースト状にする。
③カリフラワーは厚さ1センチの縦スライスにして、
ごま油を熱したフライパンに入れ、中火でじっくり両面を焼く。
④ペーストにした②をお皿に塗って③を乗せて完成。
冬至の残りで柚子があれば皮を千切りにして、
一味唐辛子と一緒に散らせば一層クリスマスらしい色合いになりますよ!
ごまとみかんの香りと一緒にぜひお楽しみください。
|
こんにちは!野菜ソムリエの知久です。]
お正月のお節料理。
最近ではお取り寄せする方が年々増えてきているようでが、
手作りにこだわりたい方もいらっしゃると思います。
ただ、年末に近づくとお正月商材が値上がりしてくるのが、
お財布には厳しいところ。
そこで今回はお節に欠かせない野菜を今のうちに購入して、
年末まで鮮度を保つ方法をご紹介したいと思います。
まず、子孫繁栄を願って使われる里芋ですが、
乾燥が大敵なので1個ずつ新聞紙に包んでから、
ポリ袋に入れて野菜室で保存してください。
先の見通しがよい縁起物として使われる蓮根。
こちらも同じような方法で野菜室にて保管可能ですが、
農家さんが教えてくれた方法は、たっぷり水を入れたバケツの中に入れ、
水を毎日欠かさず交換すると蓮根の変色も防げるそうです。
ごぼうは泥付きのものを購入し
新聞紙に包んで冷暗所に保管すれば長持ちしますよ。
ぜひお手頃価格のうちに購入してお試しくださいね!
|
こんにちは。野菜ソムリエの玉之内祐子です。
日本のお正月には欠かせないおせち料理に使われる野菜として知られる「くわい」。
漢字では「慈姑」と書き、昔から「芽が出る」縁起物として重宝されています。
オモダカ科の水生植物で、ジャガイモと同じく塊茎を食べる野菜です。
泥の中で育つ小ぶりな球形の芋のようなもので、
ホクホクとした食感とほんのりとした苦みが魅力。
だしを良く含むため、おせちでは煮しめとしてよく使われます。
旬は11月下旬から1月ごろ。
国内で流通しているくわいのほとんどは青くわいと呼ばれるもので、
青みがかった美しい皮の色が特徴です。
調理時には芽は落とさずに適当な長さに切りそろえ、
底の部分を切って下から上に皮をむくとむきやすいです。
アクが出るので、皮をむいたら水につけてアク抜きをしましょう。
出汁との相性が抜群なので含め煮にするのが一般的ですが、
意外と素揚げやフライ、クリーム煮などもおすすめです。
ぜひお試しください。
|
こんにちは!野菜ソムリエの知久です。
あっという間に師走に入り冬至も近づいてきました!
冬至に欠かせないのが柚子。
現在、柚子の生産量日本一多いのは高知県です。
意外かもしれませんが、日本最古の産地は埼玉県の毛呂山町だと言われており、
現在でもこの時期になると地域全体が柚子の黄色に覆われます。
柚子は奈良時代に中国から朝鮮を経て日本へ伝わったと推定されていますが、]
江戸時代後期の文献に毛呂山町滝ノ入地区の土産として
柚子を栽培していたと記されています。
風当りが弱く南斜面で日当たり良好、
霜がおりにくい地の利を生かして、
現在まで栽培技術が継承されています。
桂木柚子の表面はボコボコとしており、
この突起部分に香りの素となる精油が沢山詰まっていて、
他県産の柚子より香気成分が多いというエビデンスもあるようです。
香り高い皮はお料理に、果汁はポン酢に。
残りはネットに入れて冬至の柚子湯に。
余すことなく楽しみたいですね。
|
こんにちは。野菜ソムリエの玉之内祐子です。
早くも師走。
12月は冬の訪れを感じさせてくれる野菜がたくさん出回ります。
白菜、大根、ネギ、人参、春菊など
旬の冬野菜であったかいお鍋などいかがでしょうか。
おすすめの鍋料理をいくつかご紹介します。
まずは、簡単・手軽な「豚とキャベツのゴマ塩鍋」。
鍋にゴマ油をひいて火にかけ、
ざく切りにしたキャベツと豚バラ肉を入れて炒めます。
全体にまんべんなく塩を振り、お酒を1カップ注いでふたをして煮込むだけ。
キャベツがくたくたになったら完成です。
ニラやネギを加えるのもおすすめ。
そしてもう一つ、「千切り野菜と鶏つくね鍋」。
和風だしをベースに千切りの白菜と人参、大根、ネギ、
鶏のつくねを入れて煮込みます。ポン酢でもゴマだれでも合います。
千切りにすることでどれだけでも野菜が食べられそうな、飽きない味わいです。
どちらもぜひ一番大きいお鍋のふたが閉まらないくらいに野菜を盛って
火にかけてくださいね。
|
こんにちは!野菜ソムリエの知久です。
先週に引き続き、いつもの食材でパッと華やぐ
クリスマスメニューをご紹介していきたいと思います!
【材料】(作りやすい量)
・ブロッコリーベビースプラウト‥30g
・カラフルミニトマト‥5個
・きゅうり‥1/2本
・ごま油‥大さじ1
・米酢‥大さじ1
・塩みかん(青)‥小さじ1
・にんにくチューブ‥1センチ
・鳥ガラスープの素‥小さじ1/2
【作り方】
①ブロッコリーベビースプラウトを洗って水気を切る。
きゅうりをピーラーで縦にスライスして丸める。
ミニトマトは半分にカットする。
②その他の調味料を小さなボウルに入れてよく混ぜ合わせる。
③大きめのお皿の中央にドレッシンを入れた小皿を置き、
その周りに①を飾り付けて完成。
強力な抗酸化力が期待できるスルフォラファンを
成熟したものより多く含んでいるスプラウト。
リースに見立てる葉の代わりに使いやすいので、
今年のクリスマスにお試しくださいね!
|